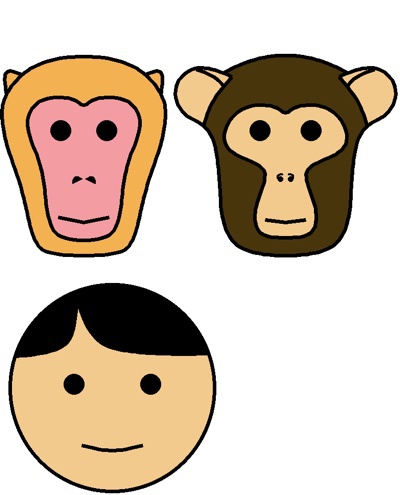最近気になっているので、書いておこうと思う。
ひとつは、環境に対する製品ライフサイクルコストのこと。
たとえば、ハイブリッド車を買う。自分が使うガソリンは少なくて済む。
だけど、製品を作ったり、廃棄するには、その差分以上のエネルギーがかかっているかもしれない。というか、多くのエンジニアは直感的にそう信じていると思う。
ハイブリッド車は、技術開発の方向性としては正しいし、それを買い支える社会も必要だ。だが、それで「いいことをした」と思ってはいけない。だって、乗らなきゃそもそも発生しないコストを生んでいるのだから。
自分の手を汚さないことと、子供たちに借金を残さないことは別。
もうひとつは、バイオエタノールのこと。
掘り出してきた石油を燃やすよりは、空気中にあった二酸化炭素からできてる植物由来の炭素を燃やす方が、二酸化炭素の増加率は押さえられる、という話だ。
でも、食糧難で苦しんでいる人たちがいるのに、トウモロコシとか米とか、そういうデンプンを材料にしたものを燃やすってどうよ? 実際、世界中でトウモロコシの価格が急騰しているらしいし、そもそも、地球上の穀物生産量はほとんど増加していない (むしろ耕地が灌漑による塩分の蓄積なんかで使えなくなり、減少に転じる方向らしい)。で、日本では養鶏業者が飼料代高騰に耐えられずに、どんどん倒産しているのだそうだ。
人間はセルロースを分解できないので、稲藁とかそういう、収穫後に余る部分を原料にできればいいんだがね。デンプンをベースにするのが酒を造るテクノロジの応用なのに対して、セルロースを元にするのは新しいテクノロジの開発になるので、難しいのはわかってるけど。
いわゆる「理系の人たち」は、こういうことを理解してちゃんと周りのひとに伝える義務があると思うわけです。どうでしょう。
投稿者: yasu
ばいよりにすと
古くからの友人の下村さんがデビューです。
みんな CD 買ってね!
finger の実装サーベイ
さる
UltraSPARC T1 と Solaris10
研究室のファイルサーバとして、UltraSPARC T1 なマシンの購入を検討中。
8 cores/chip で、4 threads/core なので、つまり最大 32 threads/chip だ。T2 という新しいプロセッサでは、これが倍の 64 threads/chip になるんだそうだ。しかも、T1 はメモリコントローラと JBus interface くらいしか集積してないが、T2 だと 10GbE とか PCIe なんかも集積している模様。すごいね。
ファイルサーバとか web サーバでは、つまり、多数のプロセスやスレッドを効率よく実行できることが重要なのであり、こういうアプローチをとる商用プロセッサがあってもいいと思う。単一のプロセスを高速に実行できるプロセッサは Intel や AMD が作っているが、SPARC だとか PowerPC なんかは、アーキテクチャ的にコンパクトなので、こういう方向へ進歩していくのはよい判断なのではないだろうか。
で、Fire T2000 買えるかなー。
LACP: 802.3ad
NFS サーバに行く Ethernet のリンクを2本とか束ねて速くしたいなー、と。
FreeBSD では ng_fec というのでできそう。
/etc/rc.conf から設定するパッチは send_pr されており、http://www.freebsd.org/cgi/query-pr.cgi?pr=104884 で見られる。
Linux にもあるみたいだ。
http://www.linuxhorizon.ro/bonding.html
腕時計その後
Alba のクォーツのやつを壊しちゃったのだけど、昨日お店から電話がかかってきて6000円で直るそうだ。
わーい。
ゼンマイの自動巻のやつは便利だが、じっと閉じこもっていたりとか、チャリに乗って生活していたり (自転車にのるときは腕時計とか付けないので) すると止まっちゃうんだよ。あたりまえだけど。
それに較べて、光発電のやつは、そのへんに置いておけば勝手に光合成 (違うって) して充電してくれるわけで、放っておいても安心。まさに永久機関というやつです (だから違うんだってば)。
gethostbyaddr
gethostbyaddr() で得られるホスト名がどうなってるか調べるには、
perl -e ‘printf(“%s¥n”, gethostbyaddr(pack(“C4”, split(/¥./, “192.168.0.XX”)), 2));’
とかすればいい。perl 便利だな。awk には gethostbyaddr() はないからな(笑)。
飯田
久しぶりに大垣行きの夜行列車に乗って、
豊橋を6時に出る天竜峡行きで信州へ。
目が覚めたら中部天竜を過ぎていて、唐笠駅でおりて下條温泉へ。
上り坂は、日差しが暑いけど、風が涼しかった。
天竜峡までタクシーで下って、また電車に乗って鼎へ。
電車の中から、Tour of Japan の日に走った赤い橋なんかが山の上にみえて、
懐かしかった。また行きたいなー。
鼎では「赤門や」にいってお菓子を買って、
向かいの cafe glam hearts でお昼ご飯。ランチは780円で大充実。
東京じゃ、1000円以上払わないと考えられない値段と内容。
飯田できんつばを買って、
飯島でまた温泉。で、帰る。
飯島駅から、中央アルプスに沈む夕陽がきれいに見えた。
一日中歩いて電車乗って、の繰り返し。それもいい。
rmt その後
FreeBSD の struct mtget は 76bytes あるが、rmt が 24bytes で切ってしまう。
xfsdump の BUFMAGIC が 64 に設定されており、76bytes 返されたら死ぬ。
というわけで、これはそれぞれあっという間に修正できるわけだが。
mt_gstat = 0 だと、drive not ready ということになってしまうらしい (笑)。そこで、猛烈に乱暴なやりかただが、rmtioctl.c で、
dstp->mt_gstat = 0;
dstp->mt_gstat |= GMT_ONLINE(0xffffffff);
と書いてみた。しかし、これではテープの終わりが正しく検出できなかったようで、
xfsdump: NOTE: dump interrupted: 18019 seconds elapsed: may resume later using -R option
xfsdump: Dump Status: INTERRUPT
ということで終わってしまった。つまり、正しく次のテープを要求させるには何らかの仕掛けが必要なのだが、これは FreeBSD 側の rmt の改造も含めて、けっこうがんばらないといけないのではないだろうか。うーん。EOT が正しく検出できればいいのかなあ。